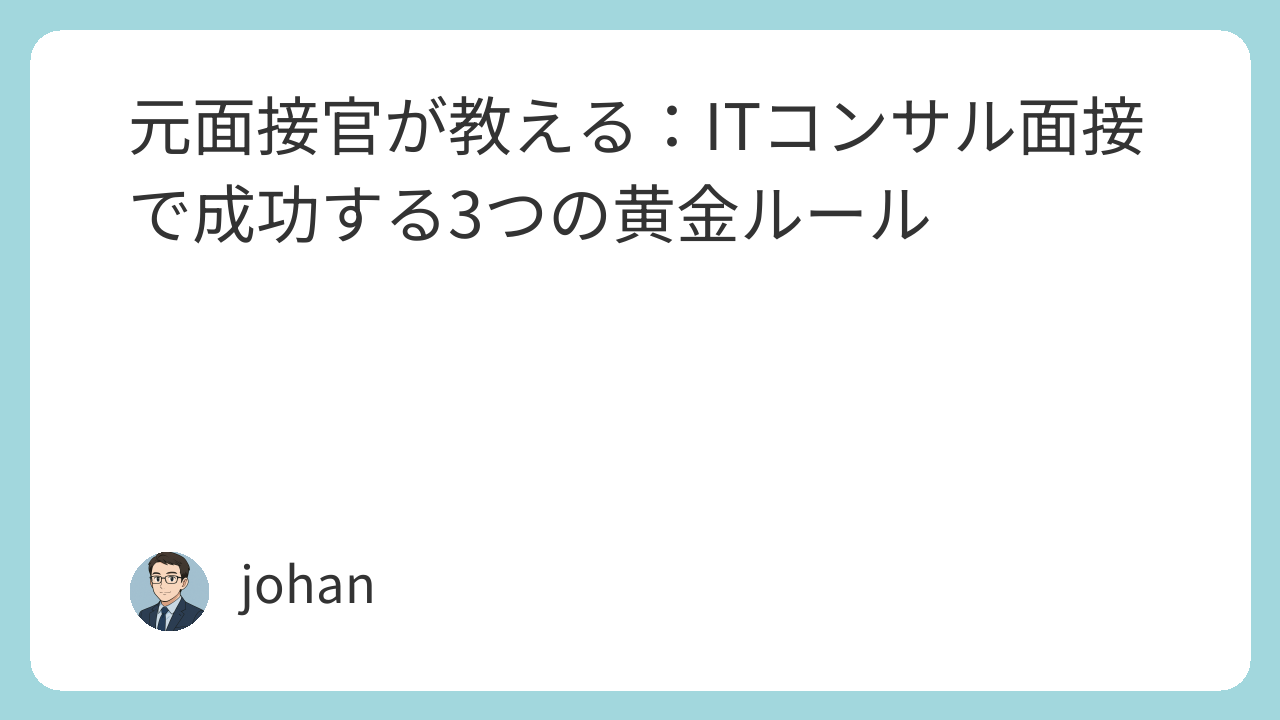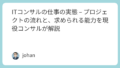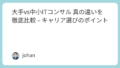大手ファームの面接官として延べ300人以上を評価してきた私が、断言します。
「ITコンサルの面接で落ちる人の8割は、評価基準を根本的に誤解している」
こんにちは、中川です。元大手メーカーから30代で戦略コンサルに転職し、現在はトップティアファームで働いています。
今回は、私が実際に面接官として使用していた評価シートの中身と、そこから逆算した「受かる人の回答パターン」を、できる限り具体的にお伝えします。
なぜこんな話をするかというと、つい先週も優秀なエンジニアの方を不採用にせざるを得なかったからです。技術力は申し分ない、実績も素晴らしい。でも、コンサル面接の「お作法」を知らないために、実力の3割も発揮できていませんでした。
なぜ技術力だけでは受からないのか?面接官の本音
まず、衝撃的な事実からお伝えします。ITコンサルの面接における評価配分は、一般的なIT企業とはまったく異なります。
| 評価項目 | 一般IT企業 | ITコンサル | 差分 |
|---|---|---|---|
| 技術力・実装スキル | 45% | 15% | -30pt |
| 論理的思考力 | 20% | 35% | +15pt |
| コミュニケーション力 | 20% | 30% | +10pt |
| ビジネス理解 | 10% | 15% | +5pt |
| カルチャーフィット | 5% | 5% | ±0pt |
見ていただいてわかる通り、技術力の配点はたったの15%です。これが「技術力が高くても落ちる」最大の理由なんです。
⚠️ 面接官として見てきた「典型的な失敗パターン」
- パターン1(45%):技術の詳細を延々と説明し、ビジネス価値を語れない
- パターン2(30%):質問の意図を理解せず、準備してきた話を一方的に話す
- パターン3(25%):話が構造化されておらず、結論が見えない
特に印象的だったのは、某メガベンチャーでテックリードを務めていた候補者のケースです。「なぜその技術選定をしたのか?」という質問に対して、フレームワークの優位性を30分も説明してくれました。でも私が知りたかったのは、ビジネス上の判断理由だったんです。
評価を劇的に上げる「3つの黄金ルール」
では、どうすれば良いのか。私が面接官時代に「この人は採用したい」と感じた候補者に共通していた、3つの要素をお教えします。
黄金ルール①:すべての回答を「構造化」する
コンサルタントにとって最も重要なスキル、それは複雑な情報を整理して伝える力です。これは回答の冒頭で「枠組み」を示すだけで、劇的に改善できます。
❌ ダメな例
「プロジェクトマネジメントの経験ですが、前職では大規模なシステム刷新を担当しまして、メンバーは20名ほどで…(延々と続く)」
✅ 良い例
「PM経験を3つの観点でご説明します。まず規模ですが20名体制で予算3億円。次に難易度として、レガシーシステムとの並行稼働が…」
実際、私が評価した候補者のデータを見ると、構造化ができている人の合格率は72%、できていない人は18%でした。この差は歴然としています。
1回答の型を決める
「3つあります」「2つの軸で」など、最初に数字を宣言する
2優先順位を示す
「重要度の高い順に」「インパクトの大きい順に」と付け加える
3結論を先に述べる
各ポイントの冒頭で、一言で要約してから詳細に入る
黄金ルール②:「So What?(だから何?)」思考を徹底する
マッキンゼーでも最重要視される思考法ですが、これは事実を価値に変換する技術です。あなたの経験や知識が、クライアント(=面接官)にとってどんな価値があるのかを明確にする必要があります。
| 質問 | 事実レベル(不合格) | So What?追加(合格) |
|---|---|---|
| 強みは? | 「Pythonで機械学習の実装が3年」 | 「機械学習で3年の経験がありますが、重要なのはビジネス課題を技術で解ける問題に再定義できること。例えば営業の属人化を顧客分類の最適化問題として…」 |
| 失敗経験は? | 「納期遅延しました」 | 「納期遅延を起こしましたが、この経験からステークホルダーマップの重要性を学び、以降は必ず作成。結果、手戻りを70%削減」 |
💡 So What?を見つける魔法の質問
自分の回答に対して、以下を3回繰り返してみてください:
- 「それによって何が変わったか?」
- 「なぜそれが重要なのか?」
- 「クライアントにとっての価値は?」
黄金ルール③:「仮説」を持って臨む
企業研究の量ではなく、深さと独自性が評価されます。公開情報から導き出した「あなたなりの仮説」を持っているかどうかで、評価は天と地ほど変わります。
✨ 実際に高評価を得た仮説の例
「御社の決算資料を3年分析析したところ、売上成長率の鈍化が見られます。原因は大企業偏重の営業戦略と推察します。私は中堅製造業での経験があるため、この層向けのパッケージ型サービスを設計し、新たな成長曲線を描けると考えています」
→ この候補者は希望年収+150万円でオファー獲得
よくある質問への「勝ちパターン」回答例
ここまでの3つのルールを使った、実際の回答例をお見せします。ただし、丸暗記は絶対にNGです。構造と思考法を理解して、自分の言葉で話すことが重要です。
Q1:なぜコンサルタントを志望するのですか?
「3つの理由があります。Push要因、Pull要因、そして個人的ミッションです。
Pushとして、現職では1社の枠内でしか価値提供できない限界を感じています。Pullとして、御社のような業界横断的な知見を活かせる環境に魅力を感じます。そして個人的には、日本企業のDXを本質から変革したいという使命感があります。
つまり、技術と経営の架け橋として、より大きなインパクトを生み出したいのです」
Q2:ケース面接「日本の電車の本数を推定してください」
「需要側と供給側の2つのアプローチで推計します。
需要側:人口1.2億×鉄道利用率40%×1日平均2回÷1本500人=約20万本/日
供給側:鉄道会社200社×平均5路線×1路線200本=約20万本/日
両アプローチで近似値となったため、1日約20万本が妥当な推定と考えます」
面接官が見ている「本当の評価ポイント」
最後に、私が300人以上を評価してきて確信していることをお伝えします。
面接の合否は、最初の10分でほぼ決まります。
なぜなら、以下の3点が開始10分で判断できるからです:
| 評価タイミング | 見ているポイント | 判断基準 |
|---|---|---|
| 0-3分 | 第一印象・話し方 | クライアントの前に出せるか |
| 3-7分 | 論理的思考力 | 構造化して話せるか |
| 7-10分 | 価値変換能力 | So What?ができるか |
私が見た中で最も印象的だったのは、ある候補者が最初の自己紹介で「私の強みを御社のコンピテンシーモデルに沿って3つご説明します」と切り出したケースです。事前準備の深さと構造化思考が一瞬で伝わり、その時点で「この人は採用だな」と確信しました。